フランチャイズ契約を結ぶときは、フランチャイズ加盟店が注意しなければいけないことがいくつもあります。
その注意点を守らないと、後でフランチャイズ本部との間でトラブルになることもあります。
注意点はいろいろありますが、そのうちの一つが【競業避止義務】です。
今回は、この競業避止義務について詳しい解説をします。
フランチャイズ契約で注意すべきことは何?

まずは、フランチャイズ契約でフランチャイズ加盟店が注意すべきことを紹介しましょう。
フランチャイズ本部に納める金額をチェック
フランチャイズ契約では、加盟店側はフランチャイズ本部から店舗経営に関する様々なサポートを受けられますが、その見返りに対価を支払います。
対価とは次のようなものです。
- 加盟金
- ロイヤリティ
- 保証金
- システム利用料や研修費など
これらの代金がどのくらいになるか確認した上で、フランチャイズ契約を結ばなければいけません。
契約期間や更新料・解約金などをチェック
フランチャイズ契約を結ぶ場合、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店の間で契約期間を定めます。
よくあるパターンが契約期間3~5年というものですが、業種やフランチャイズ本部の意向によっても変わってきます。
この契約期間をさらに延長するときに必要になるのが更新料です。
いくらくらいで更新できるのか、確認しておきましょう。
契約期間満了を迎えずに解約するときは、普通解約料が発生します。
この金額も確認事項です。
契約終了後のルールをチェック
フランチャイズ契約を結んでも後で解約したくなることもありますが、契約終了後についても契約時に取り決めが行われます。
契約終了後には商標の使用をやめることや競業避止義務(次項で概要を説明します)を守ることなどです。
この点をしっかり確認しておかないと、契約終了後にトラブルになることがあります。
フランチャイズ契約の競業避止義務とは?

ここからは記事の主題である【フランチャイズ契約の競業避止義務】について説明していきます。
この競業避止義務、一体どんな義務なのでしょうか。
詳しい内容を見てみましょう。
フランチャイズ本部と同じ、または類似の営業を行ってはいけないとする義務
競業避止義務とは、フランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部と同じ、又は類似の営業を行ってはいけない義務のことです。
フランチャイズ本部はフランチャイズ加盟店に様々な経営や販売ノウハウを伝授しますが、それはフランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部の指導の下にあるという前提によります。
あくまでもフランチャイズ本部の傘下にあるということで、サポート提供を行っているのです。
ところが、そんなフランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部と関係なく、勝手に同じ、または類似の営業を行ったらどうでしょうか。
フランチャイズ本部の持てるノウハウやスキルをそのまま盗用されてしまうことになります。
それは、フランチャイズ本部にとって大きな損失であると共に、大事なノウハウや技術が流用されることも意味します。
フランチャイズ本部がそのような事態を避けたいと思うのは当然です。
そこで、競業避止義務を設けて、フランチャイズ加盟店に一定のルールを守らせるのです。
契約期間中や契約期間後に課せられるルール
フランチャイズ契約中に競業避止義務が課せられるのは当然でしょう。
契約期間中にフランチャイズ加盟店に勝手気ままなことをさせるわけにはいきません。
しかし、この競業避止義務、フランチャイズ契約完了後も一定期間効力を発揮するようになっていることが多いです。
これも当然ですね。
契約期間が終了した後すぐに、元フランチャイズ加盟店がフランチャイズ本部と同じ、または類似の業種で営業すると、フランチャイズ本部から得たノウハウや技術をそのまま使うことになります。
契約を終了したフランチャイズ本部としても、それでは大いに困るでしょう。
自店が蓄積したノウハウや技術が契約を終了した元フランチャイズ加盟店に使われてしまえば、タダで盗まれているようなものです。
テリトリーの侵害にもなります。
フランチャイズ本部にとっては大損害といってもいいでしょう。
そのようなことを避ける意味でも、フランチャイズ本部は元フランチャイズ加盟店に契約終了後も一定期間競業避止義務を課すことになります。
法律でも説明義務が説かれている
フランチャイズの競業避止義務については、契約時の記載と説明義務に含まれています。
中小小売商業振興法第11条1項6号、同施行規則第10条10号に定められているところによると、<契約期間中又は契約の終了後の競業避止義務規程の有無及びその内容>について記載・説明すべきとしています。
競業避止義務はフランチャイズ本部にとってはとても重要

フランチャイズ本部にとって、競業避止義務をフランチャイズ加盟店に課すことは非常に重要です。
その理由を挙げてみましょう。
ブランド保護
フランチャイズ本部はその持つブランド性を非常に大切にしています。
ブランド価値を維持するためには、勝手にブランド名やノウハウ・技術が流用されるようなことがあってはいけないのです。
だからこその競業避止義務があり、フランチャイズ加盟店側に守らせることになります。
機密情報を守る
フランチャイズ契約が結ばれると、フランチャイズ本部はフランチャイズ加盟店に様々なサポートを行いますが、その中には機密情報の提供もあります。
店舗経営をする際に役立つ機密情報を教えることもあるでしょう。
この機密情報、いったんフランチャイズ加盟店オーナーに伝えたら、そのまま頭の中に残ってしまいます。
もしフランチャイズ加盟店オーナーが他店舗を起こし、この機密情報を勝手に持ち出して、利用したら大変です。
フランチャイズ本部側にとっても大きな痛手となるでしょう。
そこで、競業避止義務を課すことにより、機密情報も保護していくのです。
ノウハウの他社への流出を避ける
フランチャイズ本部が蓄積したノウハウや技術はフランチャイズ本部にとっても宝物です。
ほかの業者に使われないように大事に保護・保管しています。
しかし、もしフランチャイズ加盟店が同業種で新たな営業をするとなると、そのフランチャイズ加盟店から他社にフランチャイズ本部のノウハウや技術が流れてしまうことがあります。
これはフランチャイズ本部が最も嫌がる点です。
これらのノウハウや技術は自店舗内でのみ使うべきもので、他店に盗まれては大変な損失になります。
そこで、フランチャイズ加盟店に競業避止義務を課すことが重要になってくるのです。
ビジネスの一貫性を保つ
フランチャイズ本部としては、ビジネスの一貫性を保っていかなければいけません。
同じフランチャイズの中で同じルールに基づいてお客さまにサービス提供していく必要があるのです。
ところが、フランチャイズ加盟店が同業種で別の営業を始めると、フランチャイズ本部の有するルールが他店で使われることもあります。
違う系統のお店で同じルールが適用されているということにもなりかねないのです。
そうなると、フランチャイズチェーンのビジネスの一貫性が脅かされることにもなります。
そのような事態もフランチャイズ本部が嫌うことですから、フランチャイズ加盟店に競業避止義務を課すことが重要になってきます。
フランチャイズの競業避止義務の内容は?

フランチャイズ契約でフランチャイズ本部からフランチャイズ加盟店に課されることが多い競業避止義務ですが、その内容はどうなっているでしょうか。
内容は契約書に明記されているはずです。
それを確認すればわかることでしょうが、これからフランチャイズ契約を結ぶことを考えているオーナーもいるでしょうから、基本的な内容を紹介しましょう。
競業避止義務の範囲
一般的な競業避止義務の意味はすでに説明したとおりですが、詳細な範囲となると、フランチャイズ本部によってもルールが変わってきます。
どのような業務や活動が競業避止義務に当たるのかを契約書に明記することになります。
いくつか競業禁止の例を挙げてみましょう。
- 同業種又は類似業種で店舗を開業する
- 競合他社に就職して、店舗運営をする
- フランチャイズ本部と関係がある特定の商品やサービスを提供する
地理的範囲
フランチャイズの競業避止義務では、競業禁止の範囲と共に競業禁止の地理的範囲も定めます。
例えば、フランチャイズチェーン店が存在するエリア、特定の市区町村などで競業店舗を開かないないなどです。
フランチャイズ店の営業力が及ぶエリアということになるでしょう。
適用期間
フランチャイズの競業避止義務は無制限に課されるものではありません。
通常は一定期間になります。
フランチャイズ契約後で言うと、1~2年の期間になることが多いです。
この期間内に同業種の店舗を開いたりすると、競業避止義務違反となります。
適用される罰則
フランチャイズ加盟店が競業避止義務に違反した場合の罰則を定める必要があります。
罰則を科すルール、フランチャイズ加盟店の違反時にフランチャイズ本部が取る対応、罰則内容などが定められることになるでしょう。
フランチャイズの競業避止義務に違反したらどうなる?

フランチャイズ加盟店が競業避止義務に違反したら、どのような罰則が科せられるでしょうか。
これは各フランチャイズ本部ごとに定めることですが、一般的な事例を取り上げてみましょう。
違約金を請求されることがある
フランチャイズ加盟店が競業避止義務に違反すると、フランチャイズ本部から違約金を請求されることがあります。
契約書にその旨が記載されていれば、フランチャイズ加盟店は違約金を支払わなければいけません。
違約金の額が法外であると、公序良俗にもとるということで認められないこともありますが、一定の額なら、競業避止義務違反に対する賠償として支払うことになるでしょう。
損害賠償請求されることがある
フランチャイズ加盟店の競業避止義務違反により、フランチャイズ本部が大きな損失を受けた場合、損害賠償請求をすることがあります。
ただ、損失がいくらくらいになるかの算定は非常に難しいです。
そのため、あらかじめフランチャイズ加盟店の競業避止義務違反に対する損害賠償額が契約書に定められている場合もあります。
競業行為の差し止め
フランチャイズ加盟店が競業避止義務違反を犯していることがわかった場合、フランチャイズ本部は競業行為の差し止め請求をするでしょう。
そのような競業行為が継続して行われれば、フランチャイズ本部にとってもダメージも大きくなるので、<やめてくれ>ということです。
契約書に競業避止義務の条項があれば、その内容に従ってフランチャイズ加盟店は競業行為をやめなければいけません。
契約解除になることも
フランチャイズ契約期間中にフランチャイズ加盟店が競業避止義務に違反すると、契約解除の可能性も高いです。
フランチャイズ本部としても、そのようなフランチャイズ加盟店を許しておけないかもしれません。
このような形での契約解除になると、違約金が請求される恐れもあります。
フランチャイズの競業避止義務の適用例は?

フランチャイズの競業避止義務は実際にどのように適用されているでしょうか。
具体的な適用例を見てみましょう。
その適用例を参考に、フランチャイズ加盟店としては同じような轍を踏まないようにしたいところです。
飲食店フランチャイズの事例
全国に店舗を展開する飲食店フランチャイズA社に加盟していたフランチャイズ加盟店B店のケースです。
B店はフランチャイズ契約の終了に伴い、同じエリアで独自の店舗を開業しました。
これに不満を覚えたA社が競業避止義務に違反すると訴えたのです。
その裁判結果では、A社提供のレシピやマーケティング戦略をB店がそのまま活用していたと認められました。
つまり、競業避止義務違反であるとの裁定であり、B店は営業停止、及び損害賠償の支払いを命じられました。
教育関連フランチャイズの事例
教育関連サービスを提供するフランチャイズ本部C社の事例です。
フランチャイズ加盟店であったD氏が契約終了後、同じエリアで活動する競合サービスに就職しました。
これに気付いたC社が競業避止義務違反を主張したのです。
その結果、D氏がC社のノウハウや顧客リストを利用していることが判明。
そこで競業避止義務違反が認められ、D氏は損害賠償を支払わざるを得なくなりました。
美容サロンフランチャイズの事例
次は、美容サロンのフランチャイズ本部E社の事例です。
E社のフランチャイズ加盟店であったF氏は、フランチャイズ契約終了後に新たな別サロンを開業しました。
ところが、そこでE社が同社の顧客を引き継いでるのではとの疑いを抱いたのです。
そのために競業避止義務違反の訴えを起こします。
結果は、F氏がE氏の施術技術や顧客リストを流用していることが判明し、F氏は営業停止と損害賠償の支払いを行うことになりました。
フランチャイズの競業避止義務が無効になるケースとは?

通常は、フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店の間で契約が結ばれると、競業避止義務についての取り決めも行われ、フランチャイズ加盟店はそのルールを守らなければいけなくなります。
しかし、すべてのケースというわけではなく、競業避止義務が無効になる場合もあるのです。
そこでどのような場合に無効になる可能性があるのか、事例も含めて紹介しましょう。
職業選択の自由|営業の自由に対する不当な制約があると、無効になるケースも
フランチャイズ本部の持つノウハウなどの保護、商圏の維持に必要になる競業避止義務ですが、フランチャイズ加盟店にとっては大きな制約になります。
それが致し方ないときもあるものの、時には職業選択の自由|営業の自由に対する不当な制約となることもあります。
この不当性というところがポイントで、そのような場合、競業避止義務が無効になることがあるのです。
この点については、過去に裁判で何度も争われています。
その判例を紹介しますが、多くの判決を見てみると、次のようになっています。
競業避止義務自体は有効であっても、<その制限が過度に厳しい場合は、職業選択の自由|営業の自由に対する不当な制約が加えられるので、公序良俗の観点から効力がなくなる>とのことです。
過度に厳しいというのは、<適用期間が長すぎる><適用地域が限定されすぎている>などのケースです。
また、競業避止義務条項が有効だと認められても、違約金が高すぎるときは減額されることもあります。
競業避止義務が無効になった判決例を紹介

裁判で競業避止義務が無効になった判決例があるので、いくつか取り上げてみましょう。
労働者派遣事業のフランチャイズ契約の事例
労働者派遣事業のフランチャイズ契約に関しての競業避止義務が無効になったケースです。
フランチャイズ加盟店Bはフランチャイズ本部Aに加盟し、2期6年事業を継続しました。
その後、脱退。
そして、フランチャイズ加盟店Bは脱退後、関連会社Cに吸収合併され、C社がBの行っていた事業を継続しました。
この事態に気がついたフランチャイズ本部Aは、C社及び連帯保証人のD氏に対して、フランチャイズ契約上の競業避止義務違反に当たるとして損害賠償請求訴訟を起こしました。
本件で問題になった競業避止義務違反条項を簡単に説明しておくと、次のようになっています。
<甲は契約期間中、及び契約期間の終了後又は解除後の2年間、本件契約に基づかず乙の事業と同種又は類似の事業を行ったり参加したりすることはできない。>
元フランチャイズ加盟店のBがたとえ直接同業種の事業を興したのではなくても、吸収合併により同業種の事業を継続していることになります。
そうなると、上記の条項に違反しているようです。
競業避止義務違反自体は認められたが⋯
この事例では、裁判所によって競業避止義務違反自体は認められています。
事業を継承したのは関連会社C社ですが、そのC社が元フランチャイズ加盟店Bの権利義務を受け継いでいるということで、競業避止義務の責任を負っているとされました。
C社は元フランチャイズ加盟店Bが雇用していた技術者をそのまま雇用してBの顧客に派遣していたのですが、これはC社がフランチャイズ本部Aと同じ事業を営んでいるものとして認められました。
そのため、競業避止義務違反に当たることになったのです。
問題になったのは競業避止義務条項の効力の方
本件では競業避止義務違反が認められたのですが、ここで問題になったのが競業避止義務条項の効力です。
結論を先に言いましょう。
裁判所はこう判断しています。
<保護されるべきフランチャイズ本部の利益と元フランチャイズ加盟店Bが被る不利益を対比すると、社会通念上是認しがたい程度に達しているとして、公序良俗違反に該当し無効である。>という判決を下しました。
裁判所の示した理由は?
競業避止義務違反が認められて、その条項は無効であるとされた今回の判決。
少しわかりにくい結果になっていますが、裁判所は理由を挙げています。
- 元フランチャイズ加盟店Bが事業を営んでいた地域で、C社の商圏が成立していたとは言えない
- 元フランチャイズ加盟店Bがフランチャイズ本部Aから受け継いだ営業ノウハウは契約から6年経過しており、秘密性及び有用性を欠くことになり、保護価値がわずかになっていた
- 本件競業避止により、元フランチャイズ加盟店Bは廃業せざるを得ない状況で、廃業時のC社の態度に照らし合わせてみると、廃業に伴う対価を得られる見込みではなかった
- フランチャイズ契約終了の原因について、フランチャイズ本部Aの全国展開計画の頓挫、フランチャイズ加盟店Bにとって有益なソフト開発の放棄など、やむを得ない事情が含まれていた
これらの原因が今回の裁判所の判決につながりました。
難しい問題だが⋯
フランチャイズ契約における競業避止義務の問題は難しいポイントです。
保護されるべきフランチャイズ本部の利益と職業選択の自由ないし営業の自由が制限されるフランチャイズ加盟店側の事情のせめぎ合いになり、裁判所の判断も分かれるところです。
ただ、裁判ではフランチャイズ本部の商圏|経営ノウハウの範囲|内容|契約終了に至った原因なども詳細に分析され、判決が出されます。
今回の事例は、競業避止義務違反のありようについて考えさせられるものでしたね。
上記参照元:フランチャイズ契約における競業避止義務が無効となるとき | 弁護士によるフランチャイズトラブル相談
薬局フランチャイズの事例
今度は薬局フランチャイズのケースを取り上げてみましょう。
フランチャイズ本部Eと契約を結んでいたフランチャイズ加盟店Fは、契約終了後、2店舗について名称を変えて営業を続けていました。
これがフランチャイズ契約の競業避止義務に違反するとして、フランチャイズ本部Eが同店舗の閉店と違約金約3億3000万円を求めて、裁判を起こしました。
こちらのフランチャイズ契約書には<契約終了後2年間は同敷地内で薬局などを営んではならない。>という条項があったのですが、フランチャイズ加盟店Fのオーナーは気がつかなかったと言います。
判決はどうなった?
上記裁判の判決では、契約書の競業避止義務条項などを公序良俗違反するとして無効と判断しています。
<フランチャイズ本部Eが提供したノウハウについて契約終了後の一定期間、流出を防がなければいけなかったというほどではなかった。>というのが理由です。
元フランチャイズ加盟店Fが勝訴したということですね。
ここでも、フランチャイズ加盟店側が受ける営業の自由の制約やフランチャイズ本部が被るノウハウの流出などの不利益に対する対比により判決が下されています。
そして、裁判所は<フランチャイズ加盟店側に過度の制約になる場合は、たとえ契約条項に競業避止義務について明記されていても、公序良俗に反し無効になる。>との見解を示しています。
上記参照元:薬局フランチャイズの元フランチャイズ加盟店が勝訴、競業避止義務は「無効」 東京地裁 – 弁護士ドットコム
競業避止義務を設定する時のポイント
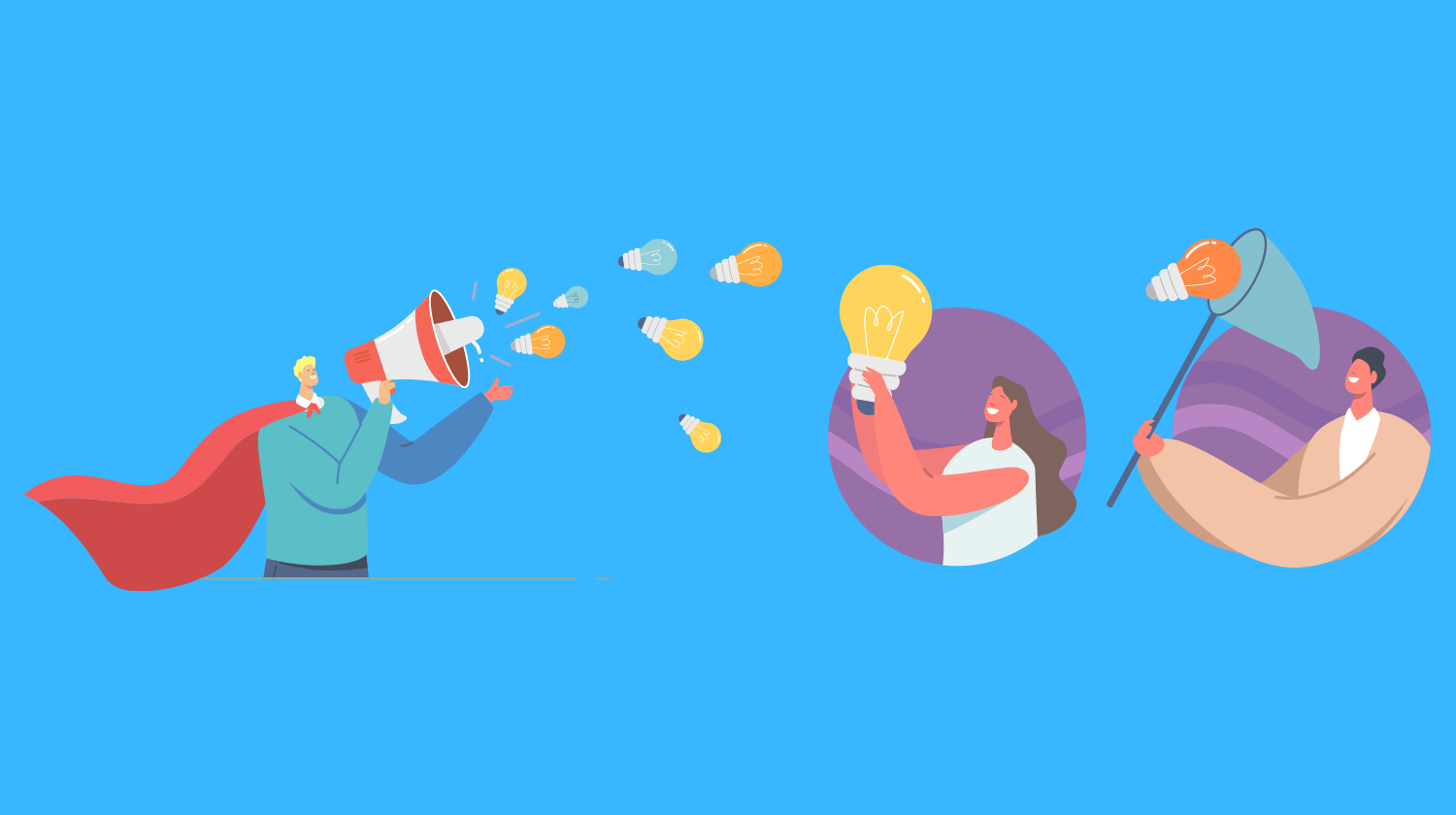
フランチャイズ契約を結ぶ場合、通常フランチャイズ本部がフランチャイズ加盟店に対して競業避止義務条項を設定します。
そこで今度はフランチャイズ本部側の視点に立って、競業避止義務の設定をするときに押さえておきたいポイントを解説しましょう。
明確かつ詳細に定義しよう
フランチャイズ契約における競業避止義務を設定するときは、フランチャイズ本部側で明確かつ詳細な定義をしておかないといけません。
曖昧な定義では、後で競業避止義務違反に問うたときに認められないこともあります。
対象となる具体的な業務内容や範囲を正確にフランチャイズ加盟店側に伝える必要があります。
適正な地理的範囲を設定しよう
フランチャイズ契約の競業避止義務条項では、対象となる地理的範囲も設定しますが、それが適正なものでないといけません。
フランチャイズの展開地域や正当な利益を保護できる範囲などを考慮しながら設定していくことになります。
期間も適正に設定しよう
競業避止義務の及ぶ期間も適正に設定する必要があります。
フランチャイズ本部としてはできるだけ長い期間、元フランチャイズ加盟店に競業避止義務を課したいでしょうが、長すぎる期間を設定すると後で無効になってしまうことがあります。
通常、適正期間というのは1~2年くらいです。
フランチャイズ加盟店への説明を尽くそう
フランチャイズ契約の競業避止義務をフランチャイズ本部側だけ理解しているというのでは、後で大きなトラブルになるかもしれません。
そのため、契約時にフランチャイズ加盟店側にしっかり丁寧に競業避止義務の内容について説明しましょう。
お互いの理解が十分進むことで、フランチャイズ加盟店側もできるだけ競業避止義務違反をしないように努めてくれます。
後でフランチャイズ本部側とフランチャイズ加盟店側に認識の齟齬が起きると、裁判沙汰になって面倒なことにもなるので、契約時のすりあわせを十分に行いましょう。
時には見直しをしてみては?
フランチャイズ本部側とフランチャイズ加盟店側の間で取り決めた競業避止義務条項をずっと適用し続ける場合もあるでしょうが、時には見直しをするのもいいかもしれません。
フランチャイズビジネスにおいては、環境や状況によって競業避止義務の役割も変化していくものです。
そのため、見直しをすることで変化に応じた適用ができるようになります。
競合避止義務の見直しポイント
フランチャイズ契約の競業避止義務を見直す際はいくつか押さえておきたいポイントがあるので、確認してください。
a,法改正に適宜・適切に対応する
法改正により競業避止義務に適用されるルールや有効性などが変わることがあるので、適宜・適切な見直しが必要になることがあります。
b,ビジネス環境の変化
フランチャイズ本部が営んでいるビジネスは展開地域・モデル・サービス導入状況などの環境が随時変化していくので、その都度見直しが必要になることがあります。
c,フランチャイズ加盟店との協議
競業避止義務の見直しはフランチャイズ加盟店と協議しながら進めましょう。
両者にとって合理的な内容になるように努め、フランチャイズ加盟店の理解と同意を得るようにします。

